改めて言う必要はないと思いますが、ビジネスにおいては話し方やコミュニケーションの取り方は非常に重要です。話し方によっては人をイライラさせてしまうこともあります。現に私も上司から指摘を受けたことも何度もあります。
その原因としては、自分本位の話し方となっていることです。本来、話す目的は相手が理解できるようにすることですが、自分が話すこと自体が目的になっていると、会話が上手くいかず、相手は不快に感じることもあります。
本記事では、コンサルタントである私が日頃意識している「人をイライラさせない」話し方を5つご紹介します。
会話のアジェンダを示す
まず、会話を行う際に何を話すのかアジェンダを明確にしましょう。アジェンダというと難しく感じますが、要は「これから話すこと」です。
聞き手は、関心のないことは聞きたくないですし、逆に関心のあることを聞けないと不安になります。これから話すことが、きちんと相手の関心と合致しているか確認することが重要です。
例えば、以下のような報告においても、何点の報告を行うか明示することで聞き手である部長は、知りたいことが報告される安心感を覚えます。逆にそれを示さないと、部長は本当に知りたいことが報告されるのか不安に感じます。また、報告すべき内容に不要なものが入っていれば、事前にその報告が不要であると伝えることができます。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長、プロジェクトの状況に関して、A社への発注状況、Bさんが担当するタスクの状況、次回の進捗会議の資料について3点報告します。 まず、A社への発注状況ですが、担当者が不在にしていたため遅延しておりますが、本日中には完了させます。 次に、Bさんが担当するタスクの状況についてですが、Bさんが体調不良になってしまったため、タスクの進捗が思わしくありません。なんとか私も加わって作業しますが、期日までに間に合わない可能性があるため、増員をお願いできないでしょうか。 最後に、次の進捗会議の資料ですが、現状踏まえマイルストンの修正を行いましたが、いかがでしょうか。 | 部長、プロジェクトの状況について報告します。 A社への発注状況ですが、担当者が不在にしていたため遅延しておりますが、本日中には完了させます。 また、Bさんが体調不良になってしまったため、タスクの進捗が思わしくありません。なんとか私も加わって作業しますが、期日までに間に合わない可能性があるため、増員をお願いできないでしょうか。 また、次の進捗会議の資料ですが、現状踏まえマイルストンの修正を行いましたが、いかがでしょうか。 |
悪い知らせ(バッドニュース)を最初に行う
次に、悪い知らせ(バッドニュース)を何より最初に行うことが重要です。
ビジネスの世界では悪い知らせを最優先で話さなければいけません。失敗や障害を後回しにしてしまうと取り返しのつかない問題につながる可能性があります。また、失敗や障害を小さいうちに早期に検知し、対策を打てば被害を最小化することができます。
会話の中でも悪い知らせを報告し忘れたり、後回しになったりしないように、初めに話すということを意識しましょう。聞き手にとっても気になる点は、問題が起きてないか、計画通りに進んでいるか、という点です。良い知らせももちろん聞きたいですが、まずは悪い知らせがないかを聞きたいものです。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長、商品Aを運送しているB社に不祥事が発生し、今後のサプライチェーンに影響を及ぼす可能性があります。商品Aの売上は非常に好調で、追加発注が多数来ています。この調子でいけば、今期の売上は競合企業に圧倒的な差をつけることができると思います。そのため、早急に別の運送業者を手配する必要があります。 | 部長、商品Aの売上は非常に好調で、追加発注が多数来ています。この調子でいけば、今期の売上は競合企業に圧倒的な差をつけることができると思います。しかし、商品Aを運送しているB社に不祥事が発生し、今後のサプライチェーンに影響を及ぼす可能性があります。 |
「結論から申し上げますと…」を冒頭に加える
「結論から話す」ということは再三語られているとは思いますが、意外にできていないことが多いです。「結論から申し上げますと…」と明示的に言うことで、結論から話すことを実践することができます。
これには、自分が結論から話すことを癖付けられるというメリットの他、聞き手が結論を明確に把握できるというメリットがあります。自分自身が結論から話すことをできていたとしても、聞き手は結論がどこか迷子になっているということもあります。これは、聞き手がちゃんと聞いていないというのも原因ですが、聞き手がどこに注目して聞けばよいかわかっていないという問題が発生しているのです。明示的に「結論から申し上げますと…」と述べることで、聞き手はどこに注目すればよいか明確になるのです。
また、結論を補足する理由についても、「その理由は…」、「理由は3点あります。1点目は…」というように明示することも同様の理由で効果的です。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長:うちの部で残業が増えてしまっているのだが、何が原因だと思う。 あなた:結論から申し上げますと、当部の社員の生産性が低下していることです。その理由としては、新しく導入した業務プロセスに慣れていない社員が多く、業務完了に時間がかかっているためです。 | 部長:うちの部で残業が増えてしまっているのだが、何が原因だと思う。 あなた:当部の社員の生産性が低下していることが原因だと思います。新しく導入した業務プロセスに慣れていない社員が多く、業務完了に時間がかかっているようです。 |
相手の質問の種類を理解する
相手の質問の種類を理解することも重要です。
質問の形式には大きく「クローズドクエスチョン」と「オープンクエスチョン」の2通りがあります。
クローズドクエスチョンとは、「はい(Yes)」か「いいえ(No)」で答えられるような質問や回答が限定されている質問です。例えば、次のような質問です。
- あなたは20歳以上ですか?
- あなたは運転免許を持っていますか?
- 会議の日程は明後日でしたよね?
次にオープンクエスチョンとは、回答を限定せずに、相手が自由に回答できる質問です。
- その趣味にはまったきっかけは何ですか?
- なぜその仕事をはじめられたのですか?
- その仕事の魅力は何ですか?
よくある例が以下の2つです。
- クローズドクエスチョンに対して、簡潔に回答せずにダラダラと話す場合
- 質問の疑問詞と回答がずれている場合
些細な違いと感じるかもしれませんが、聞き手にとっては期待していた回答が返ってこないため、不快に感じる可能性があります。
クローズドクエスチョンに対して簡潔に回答せずにダラダラと話す場合
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長:明後日のセミナーで使用する資料だが、もうできているか? あなた:いいえ、まだできていません。今、スライドの3枚目の構成で迷っており、何か良いフレームワークはないか検討を行っています。また、もう少し情報収集を行いたいと思っています。 | 部長:明後日のセミナーで使用する資料だが、もうできているか? あなた:今、スライドの3枚目の構成で迷っており、何か良いフレームワークはないか検討を行っています。また、もう少し情報収集を行いたいと思っています。 |
悪い例の方は質問に対してYes/Noで答えていないため、部長が一番知りたい資料が完成しているのか、しれないのかが明確に伝わりません。
質問の疑問詞と回答がずれている場合
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長:明後日のセミナーで使用する資料だが、いつ頃に完成しそうだ? あなた:明日の12時に完成する予定です。未完成のスライドは2枚ですので、あと6時間程度で完成すると見立てております。 | 部長:明後日のセミナーで使用する資料だが、いつ頃に完成しそうだ? あなた:未完成のスライドは2枚ですので、あと6時間程度あれば完成できると思います。 |
悪い例の方は、Whenで聞かれているのに、How longに対する回答になっています。
事実(ファクト)と見解(仮説)を区別する
会話で用いる情報には大きく2つあります。それは事実(ファクト)とそれに基づく見解(仮説)です。
事実はその意味の通り、実際に起こった、または存する事柄です。一方で、見解は物事に対する考え方や評価です。
例えば、「空に雲がある」というのは事実です。それを見て「雨が降りそうだ」と思うのは見解です。
すべての会話はこの2つを組み合わせて行っていますが、この2つを混合してしまうと誤解を招いてしまう可能性もあります。
- 事実を聞いているのに見解を答える
- 見解を聞いているのに事実を答える
事実を聞いているのに見解を答える
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長:競合のB社の今期の売上だが、昨年度と比較して増加しているか? あなた:いいえ、決算資料によると増加していません。B社は昨年立ち上げた事業の失敗が影響が尾を引いているようです。 | 部長:競合のB社の今期の売上だが、昨年度と比較して増加しているか? あなた:B社は昨年立ち上げた事業の失敗が影響が尾を引いているので、減少していると思います。 |
部長は競合B社の売上が増加しているか、否かの事実を知りたいのに、悪い例では見解を答えています。
見解を聞いているのに事実を答える
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 部長:顧客への納品だが、納期までには間に合いそうか? あなた:はい、間に合うと思います。 その理由としては、現状オンスケジュールで進んでおり、問題も発生していないからです。 | 部長:顧客への納品だが、納期までには間に合いそうか? あなた:現状、オンスケジュールで進んでいます。 |
部長は今後の納品に間に合うかどうかの見解を聞いているのですが、悪い例では現在のオンスケジュールという事実を答えています。
まとめ
以上、コンサルタントである私が日頃意識している話し方を5つ紹介しました。
いずれもポイントは、相手の立場に立ち、関心事を端的に話すということです。特に忙しいビジネスパーソンにとっては、自分の関心のないことをダラダラと話されるのは、非常にストレスを感じます。話をしていて、「あっ、この人イライラしているな」と感じた時は、相手の関心事にストレートに回答できていないことが多いです。そのような経験がある方は、日ごろの話し方を振り返り、上記で紹介した話し方を是非実践してみてください。
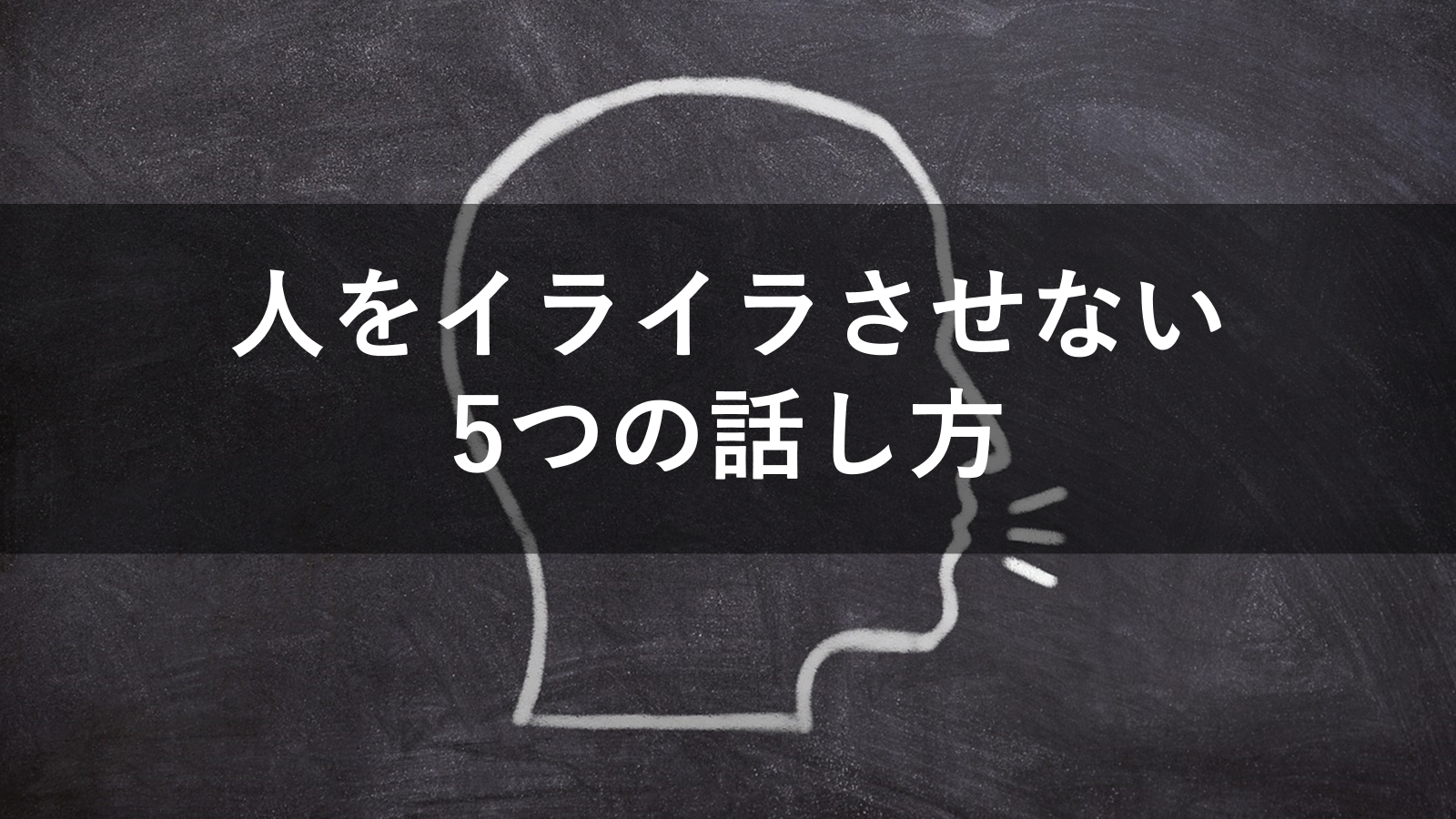
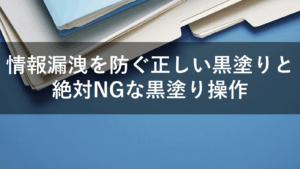
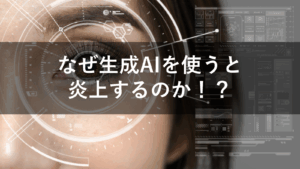

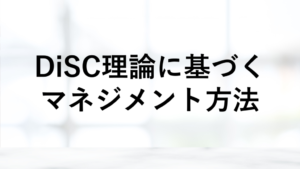
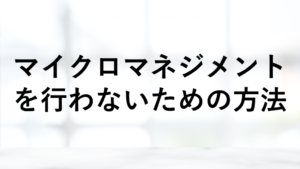
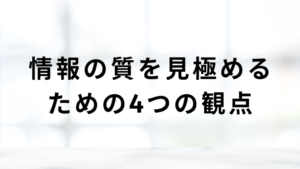
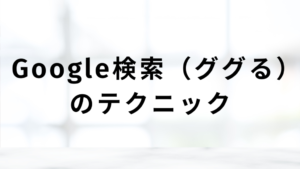
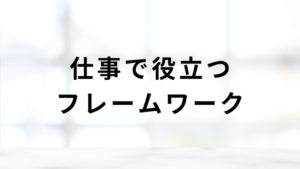
コメント