X-Techとは
「X-Tech」とは、「産業や業種を超えて、テクノロジーを活用したソリューションを提供することで、新しい価値や仕組を提供する動き」を指します(平成30年度 情報通信白書)。既存の産業にテクノロジーを組み合わせ、価値の提供方法を変えたり、新たな価値を提供したりする動きを意味します。
一般的には、「〇〇 × Technology」と表現され、〇〇には既存産業が入ります。代表例が「FinTech」です。これは金融(Finance)とテクノロジーを組み合わせた概念です。
X-Techのトレンドは今に始まったことではなく、10年以上前からX-Tech化の動きは進められてきました。それにもかかわらず、今になってX-Techを取り上げる理由は、新型コロナウイルスの感染拡大による社会の構造的変化です。新型コロナウイルスの影響により多くの人が仕事・生活の在り方を変える必要があると認識されたと思います。
コロナ禍において、「テレワーク」、「オンライン授業」、「オンライン診療」、「オンライン飲み会」等、人と人の接触を最小化するための仕事・生活の在り方が求められています。このような動きは決して新型コロナウイルスが感染している状況下の短期的なものではなく、今後の社会における新しい常識「New Normal」になると考えます。
これらの「New Normal」への変革を支えるのがテクノロジーであり、X-Tech化の流れは新型コロナウイルスの影響により更に加速することが見込まれます。企業は早期にX-Tech化の流れに対応しなければ、今後の競争に生き残ることはできず、個人もまたX-Tech化の動きに合わせて仕事・生活の様式を変えていくことが求められます。
上記を背景として企業・個人のX-Techへの対応を下支えすべく、今一度、X-Techの概念、トレンド、今後の方向性を整理したいと思います。
X-Techの背景
X-TechはFintechを皮切りに2010年代初めからスタートし、金融だけでなく他の様々な領域に展開されてきました。その背景としては大きく3つあります。
スマートデバイスの普及
①スマートデバイスの普及
スマートフォンをはじめとするスマートデバイスの普及により、人々が常にインターネットにつながっている状態ができました。スマートデバイスを通じて人々の情報が集まりやすくなり、また、企業はスマートデバイスによりアプリ・ウェブサービスを通じて、サービスを提供しやすくなりました。
②クラウドサービスの普及
AWS、Azureといったクラウドサービスの発展、価格の低下により、企業はより安価に短期間でITサービスを提供しやすくなりました。そして、クラウドサービスにより、大企業とその他企業の技術的格差が小さくなったことにより、大企業のサービスばかりでなく、より価値の高いスタートアップのサービスが消費者に選ばれるようになりました。
③データ解析技術の向上
スマートデバイスやクラウドサービスの普及により、ビッグデータと呼ばれる大量の情報が蓄積し、AIをはじめとするそれを解析する技術が進化しました。大量のデータ解析により、より顧客にとって価値の高いサービスの開発が行われるようになりました。
上記を背景として大企業ばかりでなく中小・スタートアップ企業がテクノロジーを活用したサービスの開発・提供を行うようになり、それらの競争によりX-Techの進化・高度化が進んできました。
代表的なX-Tech
前述の通りX-Techは、「〇〇 × Technology」と表現され、TechnologyにもAI、5G、ブロックチェーンというように様々な選択肢があり、その組み合わせは非常に多様です。
これらのX-Techでは、サービス・商品の提供方法を変えるものもあれば、提供するサービス・商品自体を大きく変えるものもあり、既存産業の在り方を変革させる可能性を持っています。金融では、従来の現金を使った決済方式からから電子マネー、QRコード決済が普及し、仮想通貨といった新たな金銭的な価値を持つ資産が登場しました。
今後も様々な産業に対して既存のテクノロジーや新たなテクノロジーを活用する動きは進み、産業の在り方を大きく変革させ、社会の構造的変化をもたらすことが見込まれます。
FinTech
フィンテック (Fintech) は、Financial Technology (金融技術) の略称です。金融サービスと情報技術を組み合わせ、革新的なサービスや業務の効率化、新たな金融インフラの構築を目指す分野を指します。
具体的には、以下のような技術や取り組みが含まれます:
- モバイル決済 (Apple Pay, Google Payなど)
- オンラインバンキング (ネットバンキング)
- ロボアドバイザー (自動投資サービス)
- P2P融資 (個人間融資)
- ブロックチェーン (仮想通貨取引など)
- クラウドコンピューティング (金融サービスのクラウド化)
- 人工知能 (AI) (信用審査や不正検知など)
- ビッグデータ (顧客分析やリスク管理など)
- IoT (金融サービスとモノのインターネットの融合)
フィンテックは、従来の金融サービスの課題を解決したり、革新的なサービスを提供することで、以下のようなメリットがあります:
- 利便性の向上 : モバイル決済やオンラインバンキングなどにより、時間や場所を問わず金融サービスを利用できるようになります。
- コスト削減 : フィンテック企業は、従来の金融機関よりも経費が抑えられる場合が多く、サービスの低価格化につながります。
- 透明性の向上 : フィンテックサービスは、利用者が見積もりや取引履歴などをリアルタイムで確認できる場合が多く、透明性が向上します。
- 新たな金融サービスの創出 : フィンテック技術を活用することで、従来は提供できなかったような新しい金融サービスを創出することができます。
- 金融包摂の促進 : フィンテックを活用することで、未曾有銀行サービスを利用できなかったような層 (農村地域の人々や低所得者層など) にも金融サービスを提供することが可能になります。
ただし、フィンテックにも課題があります。例えば、以下のような点が挙げられます:
- セキュリティリスク : 新しい技術を活用しているため、従来の金融機関以上にセキュリティリスクが高くなる可能性があります。
- 規制の整備 : フィンテックは急速に発展しているため、既存の規制が追いついておらず、グレーゾーンが生じる可能性があります。
- 金融格差の拡大 : フィンテックサービスを利用できるのは、インターネットやスマートフォンを利用できる層に限られてしまう可能性があります。
今後、フィンテックはさらに発展していくことが予想されます。フィンテックを活用することで、より便利で、より安価で、より透明性の高い金融サービスが提供されることが期待されます。
ReTech
X-Techの影響
X-Techによる社会への影響というのは、サービス品質の向上や新サービスの登場といった日常生活で体験できるものもあれば、企業が新たなビジネスモデルを構築し、収益を得るといった変化があります。
既存サービスの品質向上・低価格化
テクノロジーを活用し、今までの商品やサービスをより顧客の満足を得られるように改善したり、今までの作業をテクノロジーで代替し、効率化することでより安価にサービス提供をしたりすることができます。
例えば、資産運用のロボアドバイザーは、多様なデータに基づく客観的なアドバイスを短時間できるように設計されており、判断の一貫性や信頼性を担保します。また、資産運用のアドバイザーを利用するよりも低価格で利用することができます。
新規サービスの登場
テクノロジーを活用することで、今までにはなかった新たな商品・サービスを提供することができます。また、個人がスマートフォンを保有し、企業がアプリケーションを通じてサービスを提供できるようになったことで、新しいサービスを消費者に届けやすくなりました。
例えば、家計簿アプリなどはテクノロジーを活用した新規サービスと言えるでしょう。今までは紙の家計簿を使い、個人で家計を管理していましたが、アプリ上でレシートの読み取り、クレジットカード、銀行口座との連携等により、簡単に家計を管理することができるようになりました。
新しいビジネスモデルの登場
テクノロジーの活用により新たなプレイヤー、チャネルが登場し、今までのビジネスモデルが変化したり、全く新しいビジネスモデルが誕生することがあります。また、逆に今までのプレイヤーが淘汰されるといった破壊をもたらす可能性もあります。
例えば、フリマアプリは、運営会社がプラットフォームを「場」として提供し、個人間のマッチングをサポートすることで収益を得ています。インターネットを通じた顔の見えない相手との商品売買を企業が仲介することで安心・信頼を担保し、マネタイズするという新たなビジネスモデルを構築しました。
上記がX-Techの一般的な概要です。X-Techは様々な企業が様々なアプローチで取り組んでおり、非常に目まぐるしく変化している領域です。X-Techは、サービス品質を向上させる効果もあれば、既存サービスやプレイヤーを淘汰する「破壊的」な影響を持つ可能性もあります。そのため、企業のみならず個人もX-Techのトレンドや今後の方向性を理解し、変化にどのように対応すべきかをある程度知っておく必要があります。


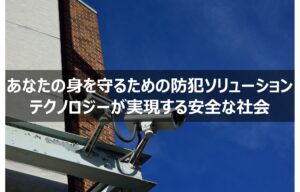
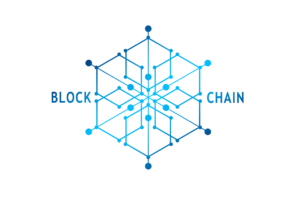





コメント